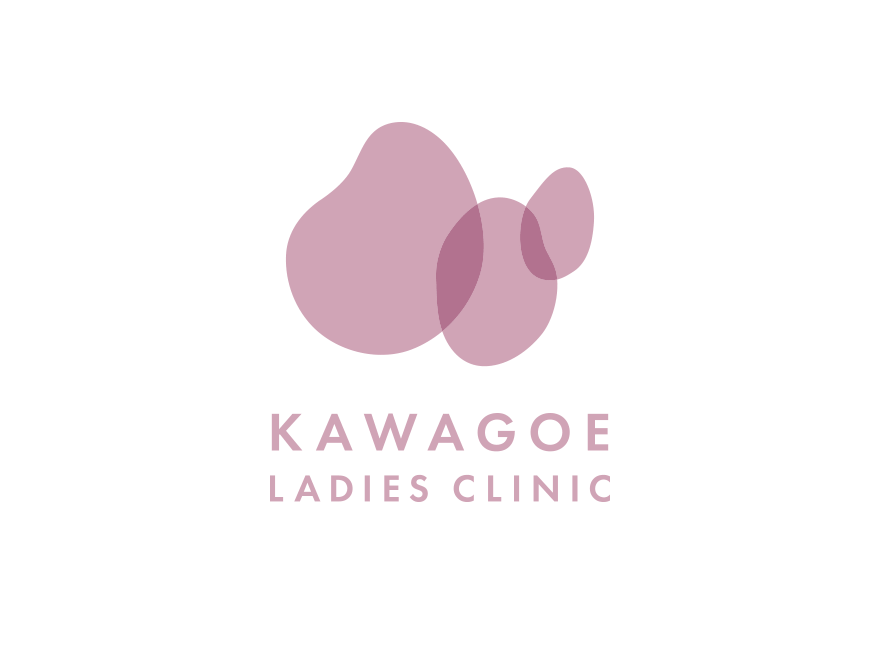細菌性膣症は、膣内の善玉菌(ラクトバチルス)と悪玉菌のバランスが崩れ、嫌気性菌が増殖することで発症する疾患です。
性行為や膣内洗浄、抗生物質の使用などが原因となることがあり、灰白色〜黄白色のおりものや魚のような強いにおいが特徴です。
症状は軽度のこともありますが、繰り返す場合には不快感が続き、他の疾患との見分けが必要です。
主な症状
細菌性膣症の代表的な症状は以下の通りです。
- 灰白色〜黄白色のおりもの
- 魚の腐ったようなにおい(特に性交後に強く感じることがある)
- 軽度の外陰部のかゆみや灼熱感
- おりものの量の増加や粘り気
膣カンジダ症やトリコモナス膣炎と異なり、かゆみが目立たないことも多く、自覚症状が乏しいまま放置されるケースもあります。
また、膣内の環境が変化しやすい生理前後や抗生物質の服用後などに発症・再発しやすくなる傾向があります。
診断方法
当クリニックでは以下の方法で診断を行っております。
問診・診察
現在の症状や発症時期、月経周期、膣内洗浄の有無、性交渉歴、過去の膣炎の経験などを丁寧にお伺いします。
必要に応じて外陰部や腟内を視診し、炎症や分泌物の状態を確認します。
おりもの検査・顕微鏡検査
おりものを採取し、顕微鏡で膣内の細菌の状態を観察します。
細菌性膣症では、ラクトバチルスの減少や「クロウ細胞」と呼ばれる特徴的な細胞の出現が見られます。性感染症やカンジダなど他の感染症との鑑別にも役立つ検査です。
pH測定
膣内のpHを測定することで、膣内環境の変化を確認します。
通常、膣内はpH4.5以下の弱酸性ですが、細菌性膣症ではpHが上昇(5.0〜6.0)していることが多く、診断の一助となります。
当クリニックでの治療方針
川越レディースクリニックでは、症状や検査結果に応じて、以下のようなお薬を用いた治療を行います。
| 薬の種類 | 目的・効果 |
|---|---|
| pH調整剤 | 膣内pHを正常化させ、膣内フローラのバランスを整えます。内服薬や膣錠として使用されます。 |
| 乳酸菌製剤 | 治療後の再発防止のため、膣内の善玉菌(ラクトバチルス)の回復を助ける目的で使用することがあります。 |
また、膣内洗浄のしすぎやデリケートゾーン用石けんの使用、香りつきナプキンの常用などが、膣内環境の乱れを引き起こすこともあります。
再発を防ぐために、生活習慣やセルフケアの見直しについても丁寧にご説明いたします。
不快な症状が続く方、繰り返す膣トラブルにお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。